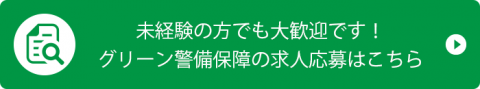【知らないと損?】交通誘導警備の給料の裏側
2025年10月31日
建設現場や道路工事のそばを通行すると、赤い誘導灯を手に持ち車や歩行者の安全を守る警備スタッフの姿を目にすることがあります。
私たちの安全な生活の裏側には、こうした「交通誘導警備」の存在が欠かせません。しかし、その仕事の対価、つまり「報酬」が、どのようにして決まっているかを知る機会は意外と少ないのではないでしょうか?
実は、交通誘導警備における報酬の根幹を支えているのが「積算(せきさん)方法」です。これは、現場に対して何人・何日・どの単価で警備員が必要かを計算するための基準のことを指します。
現場で働く警備スタッフにとっても、自分の仕事の価値がどの点で評価されているのかを理解することは、働く上で非常に重要です。
今回は、交通誘導警備の基本から、積算方法の仕組み、そして現場の実情までをわかりやすく解説していきます。
これから警備の仕事を始めようと検討している方や、現場で働いているけれど積算の意味をよく知らないという方にも役立つ内容となっています。
■そもそも交通誘導警備とは? ~警備の仕事における基礎理解~

交通誘導警備とは、道路工事や建設現場、駐車場の出入り口などにおいて、歩行者や車両の通行を安全に誘導する業務のことを指します。
主に、警備業法に基づく「2号業務」として分類されており、車両の混雑や接触事故などのリスクを未然に防ぐ、非常に重要な役割を担っています。
主な業務内容としては、以下が挙げられます。
- 建設現場の資材搬入時における歩行者の安全確保
- 道路工事中の車線規制における交通整理
- 商業施設の駐車場での出入り誘導
これらの業務は一見シンプルに見えるかもしれませんが、天候・通行量・工事内容などによって現場ごとの判断や臨機応変な対応が求められます。
警備スタッフは、現場の責任者や作業員との連携を取りながら、周囲の状況を常に把握し、最も安全かつ効率的な誘導を行う必要があります。
当社では、交通誘導警備における技術と信頼を強みとして、研修制度や安全教育にも力を入れており、警備未経験者でも安心してスタートできるよう、現場で必要な知識・スキルを段階的に学べる仕組みを整えています。
また、警備員は単なる「ただ立っている人」ではなく、現場の円滑な進行を支える「安全の要」であるという認識が、業界全体でも高まっています。この背景が、報酬に関わる「積算方法」にも大きく関わってくるのです。
■積算方法のしくみ
警備業務の報酬や見積金額は、何となく決まっているわけではありません。現場ごとに必要な人員・時間・業務内容を計算し、費用を積み上げていく手法を「積算(せきさん)」と呼びます。
特に交通誘導警備では、「1人あたり1日○円」のように提示金額の背景に、実に多くの計算と調整が行われているのです。
▶ 積算の基本構造:「人工」×「日数」×「単価」
警備業界における積算方法の基本は、いわゆる「人工(にんく)」を基準にしたものです。人工とは、「1人が1日働いた労働量」を1単位としたものです。
たとえば、2名の警備員が3日間稼働した場合、「2人 × 3日 = 6人工」となり、これに単価を掛けて積算金額が算出されます。
(例)単価16,000円の場合:
6人工 × 16,000円 = 96,000円(税別)
この「単価」は、業務内容・地域相場・資格の有無などによって変動します。
▶ 積算が決まるのはどこか?発注構造を知る
現場の積算は、通常以下の流れで行われます。
- 元請け会社(建設会社など)が交通誘導警備の必要性を判断
- 警備会社に見積りを依頼(ここで積算が発生)
- 警備会社が積算に基づいて金額を提示
- 金額が合意されれば契約成立 → 警備員の手配
つまり、積算は「現場の実態」と「警備会社の判断」が交差する地点で成立します。現場の工程や危険度によっては、警備員の人数や配置場所も柔軟に調整され、それが積算内容に反映されるのです。
▶ 積算には国の基準も存在する
実はこの「積算」には、公的な基準が存在します。
たとえば国土交通省では、毎年「土木工事積算基準」を発表しており、交通誘導警備員の配置や人工に関する考え方が整理されています。
出典:国土交通省 WEBサイト
この基準は公共工事などで用いられるものですが、民間の現場でも一部参考にされることがあり、積算の信頼性を高める指標のひとつとなっています。
▶ 警備員の給料にも反映される仕組み
積算金額は、最終的に警備員への「日給」や「時給」にも直結していきます。ただし、警備会社はその中から保険料・教育費・運営費なども賄う必要があるため、積算額=給料とはなりません。
それでも、積算の適正さが確保されていればこそ、安定的な給与体系や待遇が維持されるのです。
当社ではこの積算に関しても現場の安全性・業務効率・人材価値を加味して、適正に評価・見積もりを行っています。
■交通誘導警備の積算が「難しい理由」と「実情」

積算方法には一定の計算ルールや国の基準も存在しますが、現場での実際の運用となると「想定通りにいかないこと」が多々あります。
特に交通誘導警備においては、現場ごとに状況が異なり、積算をシンプルに機械的に処理することが難しいという事情があります。
▶ 理由①:業務内容が定型化しづらい
警備業務は「現場の条件次第」で大きく内容が変化します。
たとえば…
- 工事が繁華街か郊外か
- 交通量の多さ・歩行者の有無
- 周辺の視認性や時間帯
などの要因で、必要な警備人数や配置が大きく変動します。したがって、発注時点で正確に人員や日数を見積もるのが難しく、積算に「余白」や「安全係数」を加えざるを得ないケースもあります。
▶ 理由②:天候や工程変更など、突発的な要因が多い
交通誘導警備では、雨天中止や急な工程変更がひんぱんに発生します。
その場合、実際にスタッフが現地に行ったにもかかわらず、業務がキャンセルされることも。
- 朝礼だけで帰るケース
- 現場都合で人員過多になるケース
- 工事の遅れによる追加日程発生 など
こうした「変動リスク」も積算のズレを生む大きな要因です。日数や人工だけでは見えない、現場のリアルが積算を難しくしているのです。
▶ 理由③:積算の根拠を示すことが難しい場面も
積算は警備会社にとっては「収入の根拠」であり、元請けにとっては「コストの対象」です。
しかし、1人工を17,000円で見積もった場合、
「なぜこの単価なのか?」
「資格者がいるからか?交通量が多いからか?」などの理由を根拠として求められる場面もあります。
また、現場の複雑さ・不確実性により、その正確な説明が難しいこともしばしば。これが、積算交渉の難しさや、誤解・トラブルの火種となることもあるのです。
つまり「積算」によって、一定の基準で定められた「明確な契約金額」が存在するため、ある意味「金額や内訳は公開されている」ということになるのです。
■Q&A:交通誘導警備と積算の疑問を解消!

少々難しい内容だけに、疑問だらけだよという方も少なくないでしょう。
ここではそんな皆さんのために、交通誘導警備の積算方法について、現場スタッフや警備員志望の方からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 積算方法は警備員自身が交渉できるの?
A1.基本的にはできません。
積算は元請け企業との契約段階で警備会社が決定するものであり、個々の警備員が直接関与することはほとんどありません。ただし、正確な勤務実績の報告や現場での評価の蓄積が、将来的に給与や待遇の改善につながるケースはあります。
Q2. 積算が安く見積もられたらどうなるの?
A2.現場の負担や警備品質に影響する可能性があります。
過度に低い積算は、必要な人員配置ができなくなったり、稼働が増えても報酬が上がらない状況を生む恐れがあります。当社では、現場の実情に見合った適正な積算を常に心がけています。
Q3. 警備員の報酬にどこまで影響する?
A3.積算の精度が給与の安定性に直結します。
適正な積算がされていれば、会社側の収益構造が安定し、日給や福利厚生の充実につながります。当社では、報酬に反映できるよう現場ごとの採算も重視した運営を行っています。
【関連記事】
■まとめ:積算を知ることは、働き方を知ること
いかがでしたか?
交通誘導警備の仕事は、ただ現場に立つだけでなく、人や車の命を守る責任ある仕事です。その対価としての報酬が、どのように計算・決定されているのかを知ることは、現場で働くうえで非常に大切です。
今回紹介した「積算方法」は、警備員一人ひとりの業務価値を数値化する仕組みであり、その精度が待遇や働きやすさに直結します。現場で発生するトラブルや変動にも柔軟に対応できるよう、当社では信頼性の高い管理体制を整えています。
本記事を通じて「警備の仕事」が気になった方は、ぜひ当社で『警備の仕事』にチャレンジしてみてください。
興味がある方は、今すぐご応募を!