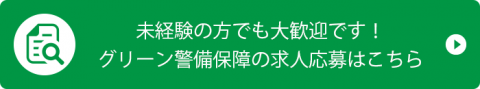『古河の歴史Vol.2編』-「支社・タウン情報」
2022年11月4日
当ブログにおいて注目を集めつつある「グリーン警備保障の支社がある街のタウン情報」ですが、今回からは、一度ご紹介した地域を「より深掘りするため」に「古河の歴史Vol.2編」と題して、前回は網羅(もうら)できなかった「古河市の歴史に関する話題」をお送りしたいと思います。
前回の内容を、より保管する形ではじまった「Vol.2」ですので、内容をすでに忘れてしまった方も多いでしょうから、まずは「古河の歴史のおさらい」からスタートです!
■まずは「古河市の歴史」を振り返ってみよう!

まずは前回のおさらいからとなりますが、この「古河市」のあたりが脚光を浴びるきっかけになったのは、歴史の授業などでも耳にする「日本最古の和歌集」である「万葉集」に、この地を表す「許我(これで「こが」と読む)」の名前が盛り込まれた歌が登場したことだそうです。
ただし、この「許我」ですが、現在の地名とはパッと見「似ても似つかない名前」になっており、本当の現在の地名のルーツであるのか?については疑わしい所、なのだそう。
その後の室町時代には、この地を拠点にしていた「古河公方」や、江戸時代に成立した「古河藩」などが存在しており、広い地域で認識・定着していた場所であったことも判明しており、おそらく人も多く住み着いていたことだったでしょう。
全国的に有名な「渡良瀬川」のおかげで「舟運・水運」もさかんであった「古河」は、その後「運送」の世界でも一大拠点となっていたようで、その流れを組んでか、1885年(明治18年)には、早くも「茨城県初の鉄道駅」が設けられるほどでありました。
ここまでが前回のおさらいとなりますが、もう一度読み返してみたい!と思った方のために、前回の記事へのリンクをご用意しました。
さて、そろそろ次のセクションにまいりましょう。
■「古河市」が同県人から「他県に属する」と思われてしまうワケとは?

続くセクションでは、一風変わったセクションタイトルが目を引きますが、一体どういうことなのか、詳しく解説していきたいと思います。
これは「古河市」の位置関係と、現在の特殊な「交通網」が関係しているそうで、前述した「渡良瀬川」の「遊水地」付近は「茨城・栃木・埼玉」の3県がひしめき合う「県境銀座」とも言える状況であり、隣県との密接な関係性に比べ、同じ「茨城県」内の地域との結びつきが「比較的薄く感じられてしまう」のだとか。
さらに「他県だと思われてしまう要因」を箇条書きで並べてみると、
・電話の市外局番が区域的に「栃木県扱い」となっている
・JR宇都宮線が走っている(管轄は「JR東日本大宮支社」である)
・一部の宅配便では「栃木県佐野市」が管轄となっている
・市内を走る「国道4号・新4号国道」は「宇都宮国道事務所」の管轄
と、やっぱり「他県だと思われてしまうポイント」がそろい過ぎていますね。
この現状ですが、意外にも「古河市」自体はかなり肯定的に捉えているようで、市の都市計画を記した「古河都市計画区域マスタープラン」上でも「さいたま新都心や宇都宮圏との連携を深めていく方向」であることを公開していますから、やっぱり「そう思われても仕方がない」と自覚しているのではないでしょうか?
■「茨城」といえば、やっぱり「舟運がさかんな地域」になるの?
続いてのお話は、この「古河市」と同様に「歴史Vol.2編」が登場している「取手市」との共通点である「舟運がさかん」という特性と、そうなっていった歴史的経緯に関するお話をお送りしていきましょう。
この「古河」における「舟運」の歴史は、多くの方々が思っているよりもずっと古く、室町時代の頃にはもう「地元の特性として認識されていた」そうです。
実際に、運送だけでなく「渡良瀬川の渡し場」として「物資だけでなく人の運搬」も行っており、その流れで「宿場町」が栄えていったわけですから、当然地元の人々も「舟運が得意な地域」という意識はあったでしょう。
さらに、江戸時代を迎える頃には、周辺の地域で採れる野菜や農産物を、一旦「古河」に集め、これまた当時から有名だった「利根川」や「江戸川」などを経由して「江戸に届ける」という重要な仕事を担っていました。
ちなみに、共通点がある「取手」は、前述の「利根川」が「舟運」の拠点となっていたため、経由地同士の交流が「確実に当時から存在していた」と考えられます。
この「江戸時代」ですが、中心地である「江戸」では、主な運送方法が後年に至るまで「河川を利用した舟運」であり、一般庶民の生活環境とも直結していた、と言われています。
実際に、最近では見る機会も減ってきた「時代劇」や「大河ドラマ」などでは、江戸を舞台としている場合でも、日常的に「河川を舟が通っている姿」が見受けられます。
紙面の関係上、これらの「舟運」の重要性については、また別の機会にご紹介できればと思いますが、現在では、一般市民との縁がなくなってしまった「河川を利用した舟運」の様子も、後世に伝えていきたい「歴史の一部」かもしれませんね。
■起源は江戸時代から?地元を沸かせる「奇祭」の歴史とは?
さて、今回最後のセクションは、他に類を見ない「奇祭」というキーワードが踊るタイトルとなっていますが、さっそく解説していきましょう。
この「奇祭」とは、地元でも定番となった「提灯竿もみまつり」のことを表しているのですが、実はこのお祭り「長さ20mほどの竿の先につけた提灯を、お互いが激しくもみ合い、相手の火を消す」という、かなり変わった趣旨のお祭りとなっており、誰が呼んだか「関東の奇祭」という異名まで備えている筋金入りの「奇祭」です。
その起源は、どうやら「江戸時代」にあったらしく、一説によると「当時の神官たちが、神社の神領である『七ヶ村』の末社をめぐり、地元に帰ってきた際に、出迎えを待っていた人たちが、寒さをしのぐためお互いの体をもみ合った」という由来があるのだそうです。
しかし、現在の祭りの内容からすると、まったく想像もつかないほど「穏やかな起源・由来」であり、現在では「高さ10mのヤグラの上での、壮絶な提灯消し合いバトル」となっているなど、聞いた人によっては、頭の中に「?マーク」が何個も浮かぶような進化を遂げてしまっています。
このような「荒々しい祭り」であるため、当時参加していた若者からは「今夜べぇだ」という掛け声が飛び交ったそうなのですが、察してしまった方も多いように、この言葉は「今夜はハメを外していい」という「大暴れ宣言」とも取れる意味なのだそうで、やっぱり当時から「奇祭」だった、と言っても過言ではなかったでしょう。
2022年12月には「第162回」を迎えるこの祭り、実は、例の「感染症」の影響により3年ぶりの開催となるため、ひときわアツい「今夜べぇ」な夜となることが予想されますので、興味のある方はぜひ足を運んでみてください!
(※古河市観光協会Webサイトより、一分内容を引用)
■まとめ:好調の「古河支社」で「グリーン警備保障」の仕事を始めよう!
さて、今回は、数ある「グリーン警備保障の支社がある街」の中から、全体で2回めとなる「古河の歴史編Vol.2」をお送りしましたが、皆さんいかがでしたか?
私たちグリーン警備保障では、今後も数多くの支社・営業所を幅広く展開していく予定ですが、その中でも「支社がある街に関する情報やエピソード」をより詳しく知り、支社だけでなく『グリーン警備保障』にとっての「地元のひとつ」として理解を深めていきたいと考えています。
地元に詳しい人材が、今後も数多く「グリーン警備保障の仕事」に携わり、さらに理解を深めていくことで、きっと私たちも、より一層「地元への愛着」を得るようになっていくでしょう。
こちらの記事を見て、地元「古河市」をはじめとする、さまざまなエリアの警備のお仕事に興味の湧いた方は、未経験者でも働きやすい、グリーン警備保障へのご応募を検討してみてはいかがでしょうか?