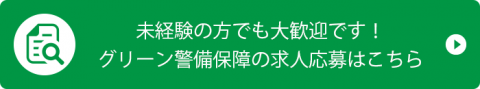『大宮の歴史編』-「支社・タウン情報」
2023年2月2日
当ブログにおいて注目を集めつつある「グリーン警備保障の支社がある街のタウン情報」ですが、今回は「大宮の歴史編」と題して、埼玉県さいたま市の一都市として、前身の「大宮市」から続く長い歴史を持つ「大宮区の歴史に関する話題」をお送りしたいと思います。(2023年は区政以降20周年のメモリアルイヤーでもあります)
というわけで、もはやお約束となった流れの中、今回もさっそく「大宮」に関する「歴史」についてバッチリ掘り下げていきますので、どうぞお楽しみに!
では、さっそく最初のセクションから!
■元々は「県名」だった? 神社・仏閣との関係も深い「大宮」とは?

さっそく今回の「大宮・大宮区」に関する歴史の話を進めていこうと思うのですが、地域の歴史について、ある程度「傾向」をつかんできた私たちや皆さんにおいては、その「大宮」という名前から、なんとなく「ルーツ」が見えてくるような気がしませんか?
実際「宮」という文字を辞書などで調べてみると「天子・神・仙人などが住む場所、御殿」という解説がされているため、セクションタイトルにもあるように「大宮という地名と寺社仏閣とは、何らかのつながりがあるのでは?」と考えた人も多いでしょう。(筆者のその一人です)
何らかの関連性に期待しつつ、この「大宮」という地名の由来を探ってみると、分かったのは「古代に『氷川神社の鳥居前町』として知られるようになり、発展していった」という事実でした。
その後、江戸時代は主に「宿場町」として栄えた「大宮」ですが、当時の隆盛を裏付ける話として「明治維新後の廃藩置県において『大宮県』が成立した」という事実があります。
当時、発展していた実績がなければ「県名を背負うほどの栄誉」が与えられるはずもなく、期待を集めた旧「大宮県」でしたが、その「わずか8ヵ月」ほどの短い歴史の間、なぜか「県庁は東京府馬喰町に置かれて」おり、その後は現在の「埼玉県」の前身である「浦和県」に含まれることとなり、その短い一生に幕を閉じるという「不遇の県名」でもありました。
ただ、そうは言っても「現・さいたま市の一角である大宮区」の立場は揺らぐことはなく、旧「大宮市」の時代も「都心から30km圏内の郊外住宅地」として、発展に継ぐ発展を遂げてきたことは、もはや説明するまでもないでしょう。(詳しくは後述します)
さて、そろそろ次のセクションにまいりましょう。
■宿場町として「江戸時代」以前から定着していた地域「大宮」

さて、先程も話に登場した「宿場町としての大宮」ですが、かつてのこの地は「中山道の一角」として、その中でも屈指の規模を誇るほどの「大きな宿場町」でありました。
その規模を知らしめるエピソードのひとつが「旧大宮宿は、中山道でも最多となる9つの『脇本陣(※注1)』を備えていた」というものです。
※注1:「脇本陣」とは、位に上下のある複数の藩・関係者が同じ宿を利用する際、位が高い方が「本陣」を使用し、他の藩は「脇本陣」を利用するしきたりとなっていた。その他「本陣に支障がある場合」などの予備としても扱われていた。
実際の所「脇本陣」が9つあるということは、それだけ「権力者の宿場利用が、この大宮宿で重なることも多かった」ともいえるので、それだけ「重要な宿場町」であったということが分かります。
さらに、基本的に本陣は、いわゆる「VIP待遇エリア」であるため「一般の利用」は許されなかったこともあり、規模の大きい「本陣」であるにも関わらず、常時使用が出来ないため、本陣や脇本陣を備えている宿場町は「売上的に余裕のある、規模や実績が大きな宿場」として認識されていたでしょう。
現在の発展にも納得が行くような、かつての「大宮」の立場は、こうしたエピソードからも容易に想像できますが、きっと全国津々浦々、各藩の要人がこぞって利用し、その凄さを認めていたはずですね。
■高度成長期の日本を支えた「ベッドタウン」の一角?「大宮」の発展期

時代は下り、舞台は再び「明治維新後」に至る頃となりますが、この頃やそれ以降の「大宮」は、一時的にではありますが、それまでの隆盛がウソのように「廃れて」しまったのだそうです。
その理由は「より近代的な『移動手段(主に鉄道)』が使用され始め、街道の利用が著しく減った」ことによるものだったのですが、1885年(明治18年)には、地元からの要望・誘致により「大宮駅」が設置されることになり、街としての難を辛くも逃れます。
その後、昭和初期を経た1940年(昭和15年)には、当時の県内で5番目となる「市政移行」を果たし、ようやく現自治体の前身となる「大宮市」が誕生する頃には、徐々に「都心に近い住宅地」としての「新たな発展」を遂げ、移住者も増加するようになったそうです。
この勢いは、戦後も途切れずに続き、特に戦後の高度成長期には、一気に人口が拡大したこともあり、前述の「大宮駅」は「東北・上越」の2つの「新幹線が通る駅」という地位を確立、街としての立場だけでなく「埼玉県内屈指の鉄道環境を誇る地域」という立場も定着させていきます。
こうして、古くも今も「人々が多く行き交う街」となった「大宮市」ですが、人の流れが大きいということは、より「商売や商業にとってのアドバンテージ」も大きくなりますので、現在の「大宮」が「埼玉県内における、商業の中心となる都市」へと成長を遂げるのも、自然な流れなのかも知れませんね。
■廃止から区政移行までの「空白の2年間」?「大宮区」の不思議とは?
さて、今回最後のセクションでは、我らが「大宮」の歩みの中でも、不思議な出来事のひとつである「大宮市から大宮区への空白の2年間」について、解説していきましょう。
ただ、かなり含みのある表現となっていますが、この「空白の2年間」は、以下のような「母体となる自治体の名称変化によるもの」です。
・2000年(平成12年)市政移行60周年
・2001年(平成13年)「浦和・大宮・与野」の3市が合併し「さいたま市」発足
・2003年(平成15年)「さいたま市」が「政令指定都市」に移行したことにより「西区・北区・大宮区・見沼区」などの「区」が成立
この流れをみれば、この「空白の2年間」の謎もまたたくまに解けるでしょうが、覚えておいてもらいたいのは、この時に発足した「大宮区」は、以前の「大宮市」のごく一部に過ぎず、本来の「大宮市だった区域」は、前述した「西区・北区・大宮区・見沼区」の4区に相当する、という状況です。
地元に長く住んでいる方であれば、この「旧大宮市と現大宮区の違い」を肌で感じていることだろうと思いますが、今後の世代にとっては「旧大宮市の規模感や地元のパワー・エネルギー」を感じられる要素が少なくなっていき、やがて「旧大宮市」のことも歴史に風化してしまう可能性もあります。
そんな中ではありますが、私たちも、今後の「大宮区」の他「旧大宮市である各区」が、発展を続ける姿を楽しみにしつつ、今回はこの辺で「大宮の歴史編」を締めることにしましょう。
■まとめ:「大宮支社」を有する「グリーン警備保障」の仕事を始めよう!
さて、今回は「グリーン警備保障の支社がある街」の中から「大宮の歴史編」をお送りしましたが、皆さんいかがでしたか?
今回の「大宮支社」ももちろんのこと、私たちグリーン警備保障では、数多くの支社・営業所で幅広く「警備の仕事」を取り扱っておりますが、まだまだ「支社がある街に関する情報やエピソード」については勉強中です。
より「地域」に密着した形で、メインとなる「交通誘導警備」を数多く任せていただけるような「信頼」を得るためにも、「支社のある街」に関する情報発信を進めていきたいと思っています。
こちらの記事を見て、地元「大宮区」をはじめとする、さまざまなエリアの警備のお仕事に興味の湧いた方は、未経験者でも働きやすい、グリーン警備保障へのご応募を検討してみてはいかがでしょうか?